![]()
国際郵便や荷物輸送
日本で普通に郵便を出す時は、手紙・ハガキ・定形外郵便などを使いますね。
重い物やかさばる物を送る時には宅配便を使うことが多いかと思います。
これと同じように、海外に何かを送りたい時には、
・ドイツの国際輸送物流会社の扱うDHL
・日本郵便の扱うEMS(国際スピード郵便)など
・ヤマト運輸の扱う国際宅配便
といった海外配送を利用することができます。
普通郵便や定形外発送の船便・航空便でも海外発送はできるのですが、到着まで一ヶ月かかったり、紛失して届かなかったりします。
国際郵便の手紙や荷物の紛失は海外ではごく当たり前のことで、届くかどうかはイチかバチか、届かなくてもまあ仕方ない、失くなったら見つからなくて当然、という状態です。
国によっては、輸出入の検査で荷物を開けて調べた時に自分が欲しいものだったらチョロまかしたり、全く違うところに配達してサインをもらって
届けたことになっていたり(適当な配送と、受け取った人が自分宛でないと分かっていて荷物を頂いてしまう悪コラボですね)、配達を忘れていて、それを申告すると怒られるので廃棄して無かったことにしたり、といったことがあります。
普通郵便であっても数日内にほぼ確実に届けてくれて、万が一失くなったらちゃんと調べてくれる日本の郵便屋さんがいかに真面目に頑張っているかというのがお分かりいただけるかと思います。
そんな海外の郵便事情ですが、せっかく出すからにはちゃんと届いて欲しいものです。
そのためには出来るだけ誤配や紛失の起こりにくい配送方法を使うしかありません。
私は海外のお友達に手紙や荷物を送る時にはいつも、荷物追跡があり、比較的早く到着するDHLかEMSを使っています。
そこで今回はEMS(国際スピード郵便)の利用方法についてご説明したいと思います。
EMS(国際スピード郵便)とは
EMSとは、Express Mail Serviceの略。
日本郵便株式会社が扱っている国際スピード郵便のことです。

主な特徴は以下のとおり。
・世界の120カ国の国に配送が可能
・速達と同等の速さで輸送されるため、比較的速く到着する
・荷物引受~配達までを追跡番号で記録しているので追跡が可能
・紛失・破損に対する損害補償がある
詳細は日本郵便サイトをご覧ください。
EMS(国際スピード郵便) – 日本郵便
EMSサービスのご案内 – 日本郵便
EMSの利用方法
まず国際郵便のダウンロードページをお気に入り登録しておくと便利です。
料金表、税関告知書、国ごとの注意事項などの主な書類はここで確認やダウンロードが可能です。
それでは、EMSで荷物を発送する際に確認すべきことや、ラベルの記入方法などを順番に見ていきましょう。
EMSの配送取り扱い国かどうか確認
まず送りたい国が、EMSの配送対応国かどうかを確認してください。
EMS(国際スピード郵便) 取り扱い国・地域一覧
配送できない国家や地域
届かない地域としては
・砂漠の中、ほぼ無人島、といった、その国の郵便事情的に無理という場所
・国家機密や軍事機密的に普通の郵便屋さんを入れるわけにはいかない場所
・疫病、紛争、治安の悪化により立ち入りが危険な場所
等があります。
例えばアメリカの配送対応に対しての注意書き。
『 アメリカ合衆国 対象地域;全域。ただし郵便番号の頭3桁が、090~098、962~966、および340で始まるアメリカの軍事基地を除く。 』
ここに示されている郵便番号は、普通の郵便局ではなくAPO、FPO、DPO のいずれかの管轄ということです。
APO:Army Post Office(陸軍郵便局) 、もしくは Air Force Post Office (空軍郵便局)
FPO:Fleet Post Office (海軍郵便局)
DPO:Diplomatic Post Office(国務省運営の外交郵便局=アメリカ大使館や領事館の管轄)
国の重要施設に危険物や盗聴器が持ち込まれたら大変ですもんね。
APO宛のEMSを配送局がうっかり通し、うっかりな郵便屋さんが持ち込んで、そこから始まるスパイ合戦に巻き込まれる郵便屋さん、ていう映画とか面白そうだなとつい思ってしまいましたが。
それにしてもブラジルが全域配送可能なのが気になります。
私がもしもアマゾン川流域に住むひとと友達になったら、EMSは届けてもらえるのでしょうか。
逆に川の流域だったら川伝いで届けられるから砂漠より届けやすいということでしょうか。
雨季と乾季で移動する民族だったら住所はどうすればいいんだろう…。
郵便局で必要なラベルや用紙をもらってくる
まず EMSの発送に必要な書類 を確認して、自分がEMSで送りたい相手国を探し、必要なのはEMSラベルだけなのか、それ以外にもインボイス等の必要な書類があるのかを確認してください。
基本的にですが、個人が個人に送るプレゼントや日用品ならEMSラベルのみでOKですし、個人間、あるいは企業間で送る商用品(売り買いするものやサンプル品)であればEMSラベル以外にインボイスが必要になります。
EMS発送用ラベルやインボイス等の添付書類はどこの郵便局にも置いてあるので、あらかじめ郵便局に立ち寄って何枚か貰ってきましょう。
最初はどれが必要か良く分からないし、記入ミスをすることもあるでしょうから、必要用紙をそれぞれ3枚ずつくらい貰ってくると安心かもしれません。
品数が多くてEMSラベルの品名欄に書ききれそうにない場合は、税関告知書補助用紙も合わせてもらっておくと良いでしょう。
大きめの郵便局ならラベルや用紙はスタンドに置いてありますし、小さな郵便局なら窓口の局員さんに言えば快くくださいます。
荷物の大きさ・重さを確認
大きさ、重さの制限があるので、梱包する箱の大きさや重さをあらかじめ確認しておきましょう。
また、送りたい国の制限についてEMSの重量・大きさ制限についてのページを確認してください。
ほとんどの国に共通する基本的な制限は・重さ 30kgまで ・最長辺の長さ 1.5m以内 ・最長辺と胴回りの合計が3m以内です。

内容物が禁制品にあたらないかを確認
国外へ持ち出してもいいもの、悪いもの(禁制品)というのは国ごとに細かく決まっています。
内容品が『禁制品(法によって輸出入が禁止されている物品)』ではないことを確認してください。
禁制品には
・EMSで禁止されているもの
・万国郵便条約で禁止されているもの
・その国が輸入規制をしているもの
などがあります。
詳細は国際郵便として送れないものと、
該当国の大使館や日本政府が発表している輸入禁止品などを確認してください。
主な禁制品は
・危険物や薬物(これは当たり前ですね)
・硬貨や紙幣(日本国内の郵便・宅配でもお金はアウトです)
・生き物(動物、昆虫)
・野菜、果物、米、小麦など
・植物の種や苗
・タバコや木炭などの植物加工品
・動物の骨や毛皮
・大量の食料
などがあります。
害虫や疫病を運ばないため、そして違法な輸出入を防ぐため、というのが主な理由です。
食べ物のほとんどがダメなの!?と思われるかもしれませんが、加工食品であればOKなことが多いので(小麦はダメだけど、うどんはOK。魚はダメでも干物や鰹節はOK、というように)禁制品かどうかよく分からない微妙な物は先に郵便局のひとに尋ねてみましょう。
お近くの郵便局の局員さんに尋ねれば該当国の禁制品一覧を調べてくれるはずですし、行くのが面倒であれば電話でお客様サービス相談センターにお尋ねください。
荷物を梱包する
EMSの発送も基本的には国内の荷物と同じく、ダンボールに緩衝材を入れて物品を入れ、テープで閉じて、発送ラベルを貼ります。
外国では荷物を放り投げるのも当たり前なので、できるだけ壊れ物は入れないよう、普通の物品を送る場合も緩衝材はしっかりと入れておきましょう。
ただし、ここで特にご注意いただきたいのが、内容物の梱包です。
禁制品や関税逃れの品を見つけるため、税関などの該当機関で国際便の荷物は開封され、内容がラベルに書かれた品名と合っているか等を確認されることがあります。
※手紙を同梱した場合、まず開けられることはないので、プライバシー的には安心していいと思います。
いざ開封検査となると、職員さん達もいちいち丁寧に開ける時間も手間もかけていられないので、綺麗にラッピングしていたとしても、リボンは解かれ包み紙は破られてガンガン開けられてしまいます。
ダンボール破れてんじゃん!カッターで中身ちょっと切れてんじゃん!とかは割と普通です。
もう最初から荷物は開けられるものとして、最初から凝った包装はやめて、どうしても個包装したい場合は中身がきちんと見える透明のビニールにしましょう。
そしてこのガンガン開けられた後に、箱は税関の味気ないテープ(大体黄色のビニールテープ)で再び閉められるので、かわいいマスキングテープ等を貼っていても、これまたムダになってしまうことがあります。
悲しいですが、これも国同士の安全と安心のためなので、郵便局員さんにクレームを言ったりはしないであげてくださいね。
そもそも郵便局で受付してもらう時にも、ラベルに書いた品名と中身が合っているか、品物によっては窓口の局員さんによる確認が必要になることもあるので閉じずに窓口に持って行って、受付OKになってから閉じたほうがいいかと思います。
その細かさと厳しさに、毎回私は「 関所を越えて御禁制の品を持ち出すこと能わず…入り鉄砲と出女…いやこれはシーボルト事件…? 」と、思わず歴史で習った江戸時代を思い出しながら受付してもらっています。
EMSの発送用ラベルを記入する

記入が必要な部分はこんな感じです。
①送り主(自分)
自分の住所・氏名・電話番号を記入
②荷受人(相手)
相手の住所・氏名・電話番号を記入
③荷物の品名と金額
内容物を英語で全て列記、数量・重さ・金額・損害要償額を記入。
内容品によってインボイス(仕入れ書)等が必要な場合は、ラベルと合わせて
窓口で確認してもらってください。
また、品物の種類がいっぱいあって、ラベルの品名欄に書ききれない場合には
他の添付用紙に書いて添える必要があります。
④確認事項にチェックを入れて署名、個数を記入
宛先・品名の詳細な記入例
品名欄に書ききれない時の対応
税関告知書やインボイスについてなどはこちらの記事をご覧ください。
EMSラベル記入例;【台湾宛】EMSのラベル記入方法
確認・受付後に荷物にラベルを貼り付け
頑張って書いたラベルでも、内容物や金額などに問題があって書き直しになる可能性が無きにしもあらずなので、荷物に貼らずに窓口に持って行き、局員さんに確認してもらってから箱に貼り付けたほうがいいかもしれません。
窓口でラベルと荷物の確認をしてもらう
中身の確認やラベルの記入が終わったら郵便局で発送依頼しましょう。
EMSの荷物も、通常のゆうパックと同じように、日本全国どこの郵便局でも受付してくれます。
田舎だと受け付けてくれないとか、大きい郵便局じゃないとダメとかはありません。
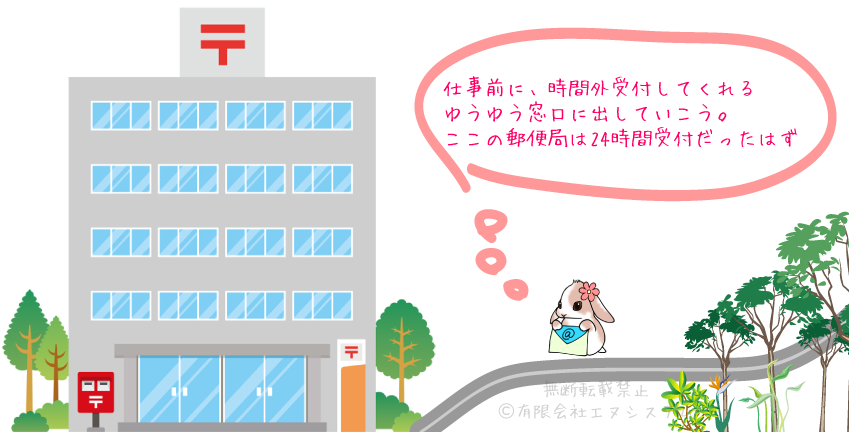
ただ、田舎の小さな郵便局だと、職員さんが今までEMSを受け付けたことがなかったりして、記載が間違っていても訂正できなかったり、受付確認に時間がかかったりすることはあります。
私もたまたま通りかかった小さな郵便局にお願いしようとしたら、
「 うどんは…セーフか?えーっと、小麦加工食品は…」
「 いやでもこの前うどん屋さんが試食用に海外に持ってったやろ 」
「 そういえばそうやったねえ、大丈夫っぽいかなあ 」
「 ちょっと待ってね、念のため大きい局のひとに聞くけんな 」
「 あぁ、あと茶葉と和三盆はどうかも聞かんといかんわ 」
「 茶葉と粉末の抹茶は扱いが違うんやったかなあ… 」
と郵便局員さん3人を悩ませ右往左往させてしまった時には『 軽い気持ちで色んな物を入れるんじゃなかった…ていうか最初から大きな局にお願いしとけば迷惑かけなかったんじゃ… 』 と思ったりしました。
サササッと手続きしたい方は、各都道府県に何軒かある特に大きな郵便局に行った方がいいのかもしれません。
EMSの荷物追跡
EMSラベルに書いてある番号を EMS配達状況確認ページ に入力すると荷物追跡することができます。
ただしこれも通常の宅配と同じで、番号が登録・反映されるまで受付から数時間かかることがあります。
荷物番号は追跡はもちろん、紛失した際の問い合わせや損害補償にも必要です。
万が一、控えを失くして番号がわからなくなってしまったら、郵便局側にも控えがあるので、依頼した日時と、送り主と荷受人の名前からきちんと問い合わせれば荷物番号を教えてくれます。
その場合は本人確認が必要になると思うので、電話ではなく、荷物を依頼した郵便局に直接行って尋ねましょう。
また、通常EMSは比較的速い配送なのですが、クリスマスから年末年始、夏季休暇のシーズンでは税関も荷物も混み合うので、かなり配送が遅れたり、紛失が起こったりします。
(例えば弊社のPC修理用部品も、お盆頃にカナダからなぜかシンガポールを経由し、最終的には中国で行方不明になったりしました)
出来る限りそういった時期を避けて送るようにしましょう。
(追記)荷物の遅延について
2020年から、新型コロナウイルス感染拡大の影響により航空便の減少や配送混雑が起き、更に税関も人員削減や消毒作業などが忙しいこともあり、海外配送の荷物が遅延しています。速達扱いのEMSであっても到着まで2週間以上かかることも。更に混み合う年末年始ともなれば1ヶ月以上かかってもおかしくない状態に。
こんなご時世、荷物を届けてくれるだけで有り難いので、荷物が中々届かなくても気長に待ってあげてくださいね。


